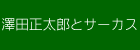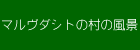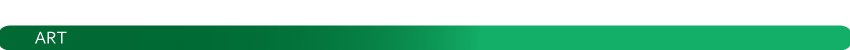
このコーナーは写真や絵画などの媒体で表現したものを紹介するスペースです。「これがアートなの」といぶかる人もいるでしょうが、広義にかつ主観的に解釈して、なんでも突っ込んで充実させていく予定でいます。


澤田正太郎とサーカスの記録
ここで紹介する写真を撮影したのは、油絵や水彩画を中心に制作した画家、澤田正太郎である。
彼の残した作品は風景画が多くを占めている。私は繊細な筆遣いと確かな存在感のある彼の絵が好きで
30年以上も前から、一つ、二つと手に入れてきた。時には欲しい絵をイラン滞在時に購入したペルシア絨毯と
交換で譲っていただいたこともある。画歴は1996年に79歳で亡くなった後に刊行された『澤田正太郎画集』
(形文社)で辿ることができるが、サーカスや遊園地をテーマにしていた時代があったことを私はこの画集で
はじめて知った。その後、彼が写したたくさんのサーカスの写真が整理もされずに眠っていることを知った。
ネガやプリントされた写真はカビが生え色あせたものも多く、整理と修復がまず必要であった。
澤田は生涯をかけ簡単なメモのような日記を残している。この日記によると1957年から59年にかけ興行
していたサーカス団を頻繁に訪れ、写真を撮り、またスケッチをしている。時代はまだ日本にサーカス団が
たくさんあり、あちこちでサーカステントが張られていた頃である。キグレ、オリエンタル、ゴールド、
矢野サーカスといった今ではその姿を見ることができないサーカスが人々の生活の中に生きていた時代であった。
新宿コマ劇場のような既設の劇場での興行もあったが、ほとんどが空地にテントを張っていた。
場所は二子玉川、新小岩、王子、大森や高円寺のような中心から少し外れたところが多かったようだ。
写真は舞台の写真だけでなくテントの設置や舞台裏の風景もあり、今では見ることのできない貴重な
記録となっている。
サーカス団の人々との交流も深く、残された写真を見ると人々の表情は実に自然で、サーカスの人々に
向けた澤田の気持ちが伝わってくる。馬の曲芸もいくつかのサーカス団で行われていた。とくにキグレや
シバタサーカスでは動物のショーに力を入れ、象、トラ、猿やカンガルーまでいたのには驚かされる。
1959年夏にはチェコからサーカス団が来日した。アラブ種の馬の曲芸が売りの一つだったらしい。
澤田はこれにも毎日のように通い、写真撮影やスケッチをしている。
写真自体貴重な資料となるが、記録のための写真やプロの写真家のそれと違い、画家の目線が
映し出されていて興味深い。澤田の父である新国劇創設者澤田正二郎が芸術と大衆を意識した
芝居を追い求めていたその精神を澤田の作品にも感じることができる。ここではほんの一部の写真しか
紹介できないが、1950年代に大衆を惹きつけたサーカスと澤田の感性を感じてもらえばと思う。